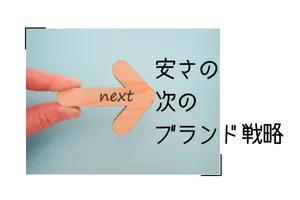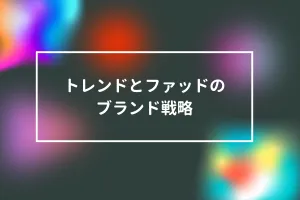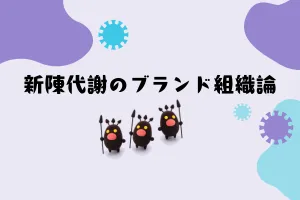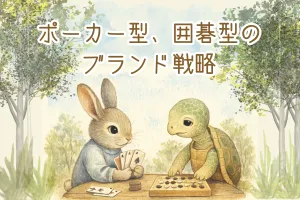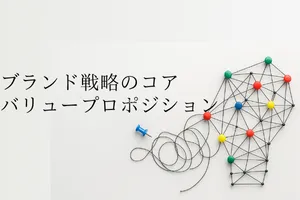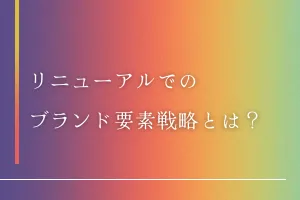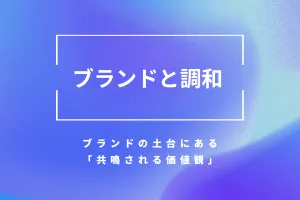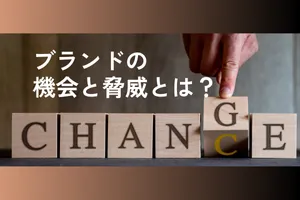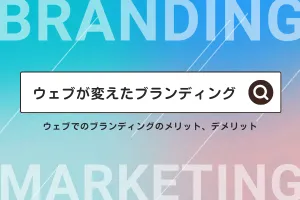ブランドの機会と脅威とは?
配信日:2025年4月2日
前回のメルマガで、強みと弱みは「解釈による」という話をしました。ブランドの強み・弱みは、企業が自分たちで決めるものではなく、顧客の視点でどう解釈されるかによって変わります。同じように、機会と脅威も「解釈次第」で姿を変える ことをご存じでしょうか?
機会と脅威は表裏一体
機会(Opportunity)とは、顧客の変化や市場のシフトをポジティブに捉え、ブランドが新たな価値を提供できる余白です。一方、脅威(Threat)は、同じ変化をネガティブに解釈し、ブランドがリスクを抱える可能性がある状況です。しかし、重要なのは 「同じ事象でも、解釈次第で機会にも脅威にもなり得る」という点です。
たとえば、AIの台頭はあるブランドにとっては 「人間の役割を奪う脅威」 に見えますが、別のブランドにとっては 「新しい顧客価値を生む機会」 と映ります。同じ変化をどう解釈するかで、未来の戦略は大きく変わるのです。
機会に見えるものが、実は脅威かもしれない
ここで注意したいのは、「機会を過大評価する危険性」 です。市場の変化を機会として捉えたいあまりに、「都合の良い解釈」 をしてしまうことがあります。
典型的なのが、「消費量が減少している=ライトユーザーが増えている」という楽観的な解釈 です。「ヘビーユーザーの離脱が減少の原因」と思いたい気持ちは理解できますが、実際には ライトユーザーも同時に離脱しており、市場そのものが縮小しているケース も珍しくありません。
さらに、消費量の減少は 「異なるカテゴリーへのシフト」 が起きている兆候である可能性もあります。単に市場が減ったのではなく、「顧客の価値観が変わり、別の選択肢に移行している」 という文脈で読み解くべき状況も多いのです。
脅威に見えるものが、実は機会かもしれない
逆に、「脅威を過大評価することで、チャンスを逃してしまう」 というケースもあります。 競合の新しい商品や、顧客のニーズの変化が 「市場の脅威」 に見えてしまい、ブランドの動きが鈍ることがあります。しかし、その脅威の裏側には 「新しい未充足市場」 が隠れている場合も多いのです。
たとえば、Z世代の“ミニマル消費”は 「購買意欲低下の脅威」 に見えがちですが、「サステナブル消費という新たな価値観へのシフト」 と読み替えれば、ブランドが新しい文脈でアプローチする機会に変わります。
機会と脅威を正しく解釈するための二重仮説
機会と脅威を解釈する際に大切なのは、「必ず二重仮説を立てること」 です。1つの仮説だけに頼ると、解釈のバイアスがかかり、都合の良いストーリーだけが見えてしまいます。
- 仮説A
- 消費量が減っているのは、ライトユーザーが増えて市場が安定しているサインである。(機会)
- 仮説B
- ライトユーザーも離脱しており、市場自体が縮小している兆候である。(脅威)
両方の仮説を立てて検証することで、現実に近い解釈を導き出すことができます。「機会に見えるものほど、脅威の視点で疑う」 ことが、ブランドの未来を守る鍵となるのです。
解釈のフレームを変えれば、未来は変えられる
機会と脅威は、単なる市場環境の変化ではありません。「その変化をどう解釈するか?」 が、ブランド戦略の命運を分けます。「脅威を機会に変える」という言葉だけに踊らされず、「都合の良い解釈に流されていないか?」「別の文脈で捉え直す余地はないか?」という問いを持ち続けることで、ブランドは真の機会を見出し、脅威を乗り越える力を手に入れることができるのです。