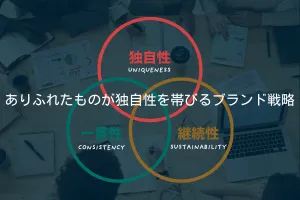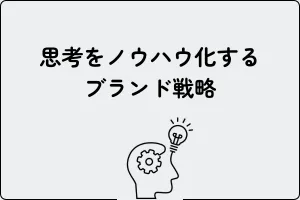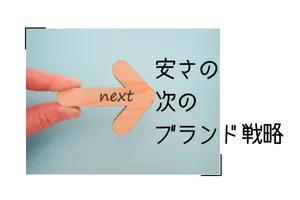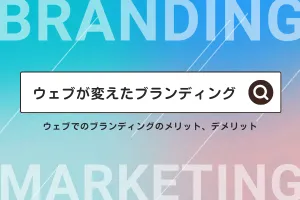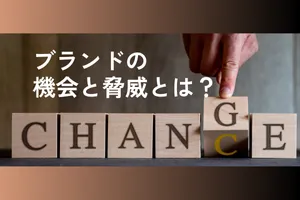偉大なマーケターと酒
配信日:2026年1月7日
今回は謹賀新年バージョンとして、こんなテーマを選びました。「偉大なマーケターと酒」。世の中ではアルコール人口が減っていると言われています。健康志向やライフスタイルの変化など理由はいろいろあるのでしょう。ただ一方で、お酒は単に酔っぱらうためのものではなく、長い歴史の中で人間の思考や関係性に独特の役割を果たしてきました。ときに思考をほぐし、ときに本音を引き出し、ときに大胆な決断を後押しする。そんな側面に目を向けてみたいと思います。
なお、今回紹介する各エピソードは、「象徴的な話として語られる逸話」を元にしています。必ずしも一つの確定した歴史資料や、信頼できる一次ソースとしてURLで示せるものではありません。公的に語られた証言や一次資料は見当たらず、多くはインタビューや社内文化を語る文脈の中で、「しばしばワインが登場した」といった形で語られてきた話です。とはいえ、どれも人と仕事、意思決定や創造性の関係を考えるうえで、とても示唆に富んだ話でもあります。面白いので、あえて紹介します。肩の力を抜いて読んで下さい。では、いきましょう。
一杯目:スティーブ・ジョブズ×ワイン

スティーブ・ジョブズは、日常的に酒を嗜むタイプではなかったと言われていますが、部下と深い議論をするときには、カリフォルニアの白ワインを口にすることがありました。強烈なビジョンを持つがゆえに、Appleの会議はしばしば緊張感に満ち、「それはクソだ」という一言で企画が吹き飛ぶことも珍しくなかったと言われています。
そんな場面でも、ワインが一杯入ると、あの鋭すぎる言葉の角が少し丸くなったとも語られています。完璧を求め続けたジョブズにとって、ワインは妥協ではなく、他者の視点を受け入れるための緩衝材だったのかもしれません。ビジョンの強さと柔らかさ。その両立は、マーケターにとっても永遠のテーマです。
二杯目:ジェフ・ベゾス×テキーラ

ジェフ・ベゾスが飲むのは、テキーラを一杯だけ。それも酔うためではなく、「発想の枠を外すための1ショット」だと言われています。Amazonには「失敗してもいいからやれ」「Day 1哲学(Day One)=いつも“創業初日”のように考えるという、Amazonの公式思想」という文化がありますが、その背景には、この“ほんの少しだけ壊す感覚”があったとも言われています。
数字や合理性を徹底的に重視する一方で、最後の一歩は大胆に踏み出す。そのスイッチとしてのテキーラ一杯。マーケターもまた、データに詰まったときほど、ほんの一歩の無謀さが必要になる場面があります。
三杯目:ウィンストン・チャーチル×ウィスキー

ウィンストン・チャーチルといえば、朝からウィスキー、昼にはシャンパンという豪快なイメージがあります。しかし興味深いのは、重要な作戦会議の前には、あえて薄めたウィスキー・ソーダを飲んでいたという逸話です。
恐怖を消すために酔うのではなく、恐怖と勇気のバランスを保つために薄めるという発想です。この感覚は、戦時下の意思決定だけでなく、現代のマーケティングにも通じます。大胆さと慎重さ。その配合を間違えないことが、結果を左右するのです。
四杯目:アーネスト・シャクルトン×ブランデー

南極探検で絶望的な状況に追い込まれたとき、探検家シャクルトンは、貴重なブランデーを仲間に分け与えました。それは体を温めるため以上に、「私たちはまだ一緒だ」というメッセージだったのでしょう。
極限状態でチームを率いた彼のリーダーシップは、ロジックよりも関係性を重視するものでした。マーケティングの修羅場でも、最後にチームを救うのは、戦略資料ではなく、人の気持ちをつなぐ象徴的な行為だったりします。
五杯目:アンディ・ウォーホル×シャンパン

アンディ・ウォーホルは、パーティでシャンパンを飲みながら、人々の振る舞いを静かに観察していたと言われています。「酔うためじゃなく、観察するために飲む」という言葉は、どこかユーモラスでありながら本質的です。
彼はアーティストであると同時に、極めて優れた人間観察者でもありました。マーケターの仕事も結局は同じです。人はなぜ惹かれ、なぜ語り、なぜ選ぶのか。酒の席は、そのすべてが露わになる舞台でもあります。
六杯目:松下幸之助×日本酒

松下幸之助は、派手に酒を飲む経営者ではありませんでしたが、日本酒をゆっくりと嗜みながら人の話を聞く時間を大切にしていたと言われています。松下電器(現パナソニック)では、「まず人を知れ」「相手の立場で考えよ」という姿勢が徹底されていましたが、その原点には、酒の席での静かな対話があったのでしょう。
日本酒は酔っぱらって「場を壊す酒」ではなく、「場を整える酒」です。声を荒げることもなく、相手を論破することもなく、ただ話を聞く。マーケターにとっても、正解を押し付けるより、相手の言葉を引き出す力のほうが、結果的にブランドを強くすることがあります。松下幸之助の日本酒は、そのための“間”をつくる一杯だったのかもしれません。
七杯目:ピーター・ドラッカー×ビール

ピーター・ドラッカーはウィーン出身で、晩年はアメリカに移ってからもビール党だったと言われています。経営者との対話の場でビールを飲むと、相手の肩の力が抜け、本音が出やすくなる。彼はそんなことを語っていたそうです。
ブランドの仕事は、ときに「正しいこと」や「あるべき論」が前に出すぎてしまい、建前が積み重なりがちです。そんな場面で、ビール一杯が場をフラットにし、物事を本質から語るスイッチになる。効率や理論だけではなく、人間そのものを見ていた、いかにもドラッカーらしい静かで実践的なエピソードだと言えるでしょう。
シメの水:酒は「知恵の小道具」だった

酒と人類の歴史は、ほぼ同じくらいの長さなのではないでしょうか。なぜなら酒は、人と人との関係性を近づけるための装置として使われ続けてきたからです。大事な顧客との会食、信頼関係を築きたい相手と向き合うとき、あるいは好きな誰かと関係を深めるとき、そこには酒がありました。コーヒーや水では、こうはいかない場面が確かに存在します。
酒は「酔う」以上に「知恵の小道具」でした。思考の邪魔をするものではなく、創造や決断、人間関係のスイッチとして使われてきたのです。マーケターに必要なのは、その一杯をどう使うか。その姿勢なのかもしれません。