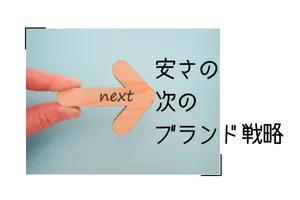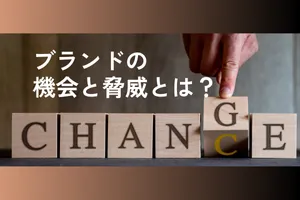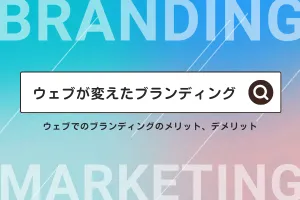業界を乗っ取るブランド戦略
配信日:2025年12月24日
ネットフリックスによるワーナー買収をめぐる騒動は、金額の派手さ以上に「業界全体の前提」を揺さぶっています。映画制作、配給、劇場公開、DVD流通という長年の流れが、ネットフリックスの一手によって一気に書き換えられる可能性があるからです。ハリウッドの脚本家組合や俳優組合は「雇用が失われる」「多様性が減る」と警戒し、映画館団体は最大の脅威だと訴え、政治家は独占を懸念して介入を示唆する。つまり既存勢力が一斉にざわついている。
では、なぜこんなに揺れるのか。ニュースだけを読むと「単なる巨大M&A」に見えますが、その背景には「もっと深い構造問題」があります。映画業界は長年、利害関係者が多く、コストも重く、意思決定が極端に遅くなっていました。作品の価値はあるのに、それを届ける仕組みが複雑すぎる。そこでネットフリックスは、おそらくこう考えたのではないでしょうか。「業界全体の疲弊や旧習を壊し、価値あるコンテンツを効率的に世界へ届けるには、決定権そのものを買ってしまうほうがいい」と。つまり、「業界の決め方ごと買う」という判断です。これはネットフリックスの思想というより、経営としてのリアリズムに近い動きだと感じます。
同じ構図はアップルと音楽業界でも起きた
この構図は初めてではありません。最も有名なのは、アップルが音楽業界に介入したときです。当時の音楽業界は、CD流通・レーベル契約・価格統制・違法ダウンロードの混乱が限界に達していました。アーティストも消費者も不満を抱え、しかし業界内部からは何も変えられない。
そこにアップルが登場しました。彼らは「音楽文化を救う」とは言わずに、iTunesという単一の窓口で「価格」「購入」「音楽体験」「関係者管理」をまとめてしまいました。当初、レーベルは激しく反発し、「音楽の価値が壊れる」「業界の主導権が奪われる」と声を荒らげた。しかし、生活者にとってはシンプルで便利な体験が広がり、結果として違法DLは減り、音楽消費は回復しました。アップルもまた「決定権を買った企業」だったと言えるでしょう。
アマゾンと書籍業界、グーグルと広告業界にも同じ波
アマゾンが書籍業界に入り込んだときも、状況は似ていました。出版社、取次、書店という複雑な構造の中で、価格も供給も棚取りも、誰が決定権を持つのかが不明瞭だった。結果、読者は欲しい本に辿りつけず、物流も非効率。そこにアマゾンが、巨大な在庫・高速配送・レビュー文化を武器に参入します。書店は反発し「文化の破壊者だ」と叫びましたが、読者はアマゾンを選びました。なぜか。「決める人が不在だった業界に、一人の決定者が現れたから」です。
広告業界でも同じです。長年、広告は経験と勘、人脈で動く世界でした。それをグーグルがアルゴリズムとデータで最適化し、広告の「出し方」「出され方」「測り方」のルールを事実上握ってしまった。既存の広告業界は猛反発しながらも、最終的に新しい標準に従わざるを得なかった。まさに「業界のOSが書き換わる」を、私たちマーケターも経験しています。
共通するのは「決め方が壊れていた業界」
これらの事例に共通しているのは、業界そのものが疲弊していたことでしょう。関係者が多すぎて意思決定が遅く、生活者の体験は改善されず、内部から変革が起こらない。そんな業界に外部からやって来るのが、アップル、アマゾン、グーグル、そしてネットフリックスのような企業です。彼らは「支配したい」のではなく、「このままでは回らない」と判断して、決定権の置き場所そのものを変えただけです。
いま顕在化しているのは「業界単位のブランド戦略」
ここまで見ると、もはや企業単位のM&Aは今起きていることの本質ではありません。本当に起きているのは、業界のテイクオーバー(乗っ取り)です。これは見方を変えると「企業が強くなる」ためではなく、「業界が持続可能な形に戻る」ために発生しているとも言えます。そして、その結果として業界の主語(決定権をもつ企業)が入れ替わるわけです。
つまり、これらのブランド戦略は「どう好かれるか」「何を語るか」という枠を越えています。業界が決められなくなっている領域で、誰が「決める側」に立つのか。その覚悟と構造を持てる企業こそが、自然と「業界を乗っ取るブランド」になっていくのです。